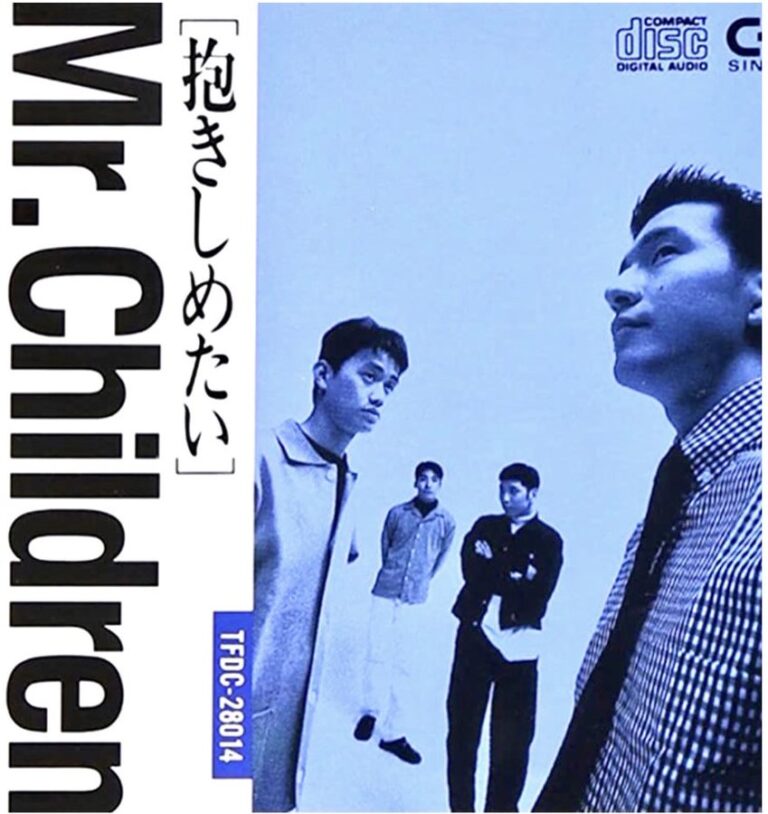楽曲制作オンライン講座を制作します。
突然ですが、オンライン講座を制作することにしました。
私は作曲家・アレンジャーとして、J-Popの制作やCM音楽、ゲーム音楽などに携わった後、Production Musicコンポーザーとして約10年間、海外のTV、映画、ラジオ向けの音楽を制作してきました。
これまでのキャリアを合計すると約20年、制作した楽曲はProduction Musicとして約2000曲、それ以前の作品も含めると約3000曲に達します。
残念ながら、私の名前を広く知られるような大ヒット曲を生み出すことはできませんでしたが、膨大な楽曲制作を通じて、多くの失敗や発見を経験してきました。
Production Musicビジネスの現状
このブログで主に取り上げている海外のProduction Musicビジネスですが、現在、楽曲生成AIの影響を受け、大きな転換点にあると感じています。
ただし、今すぐに人間の作曲家が淘汰されるというわけではありません。私自身、これまでと変わらずProduction Music Libraryと契約を結び、P.R.Oから収益を得ています。
しかし、5年後や10年後にはこの状況がどう変わるか、正直なところ全く予測できません。
これまでブログやnoteでProduction Musicビジネスに参入したい方向けの記事を執筆してきました。ただ、軌道に乗るまでに3~5年かかるこの分野に、今新たに人を呼び込むべきかどうか悩み、現在は新規記事を控えています。
AIの進化によって作曲家が淘汰される可能性もあれば、逆にAIによって新たな市場が開かれ、より活躍できる場が増える可能性もあります。現時点では、その未来はわかりません。
Production Musicでは、数多くの楽曲を契約することが重要でした。しかし、AIがこの業界に参入してきた場合、量産されたシンプルな楽曲ではAIに太刀打ちできないと考えています。
そのため、AIが作りにくい、または苦手とする分野に注力した楽曲制作が必要だと感じています。突き詰めて考えた結果、豊かな感情表現があり、強いこだわりやクセを持ったユニークな楽曲こそが、これからの強みになるのではないかと思ってい制作スタイルをその様に変えました。
Production Music Composerはアーティストではなく、サービス提供者であり職人であるべきだというのが私のこれまでのスタンスでしたが、AIの登場により、職人でありつつ、アーティスト的である事が求められる様になるでしょう。
私は、自分ができるところまでやると覚悟を決めていますが、万が一完全に淘汰された場合に備え、少しずつ制作のスタイルを変えたり、全く違う挑戦を始めたりしています。
そのうちの一つがこのオンライン講座の制作です。
オンライン講座の内容
オンライン講座の中身としては、私の楽曲制作手法を余すところなく公開し、解説するものを考えています。楽曲はもちろん私のオリジナル楽曲です。内容としては、Pop、Rock、Jazzといった定番的なジャンルに私なりの解釈を加えたもの、クリエイティビティを全開で発揮したアーティスティックな作品、さらにはProduction Musicで需要が高いDramatic TensionやDramedyといった定番ジャンルの楽曲も含める予定です。
この講座の一番の特徴は、「レクチャーしない」という点です。
どういうことかというと、「これが正解だから真似しなさい」や「こういう風にしないと失敗するよ」といった指示をしないということです。なぜかというと、私自身がそういうことを言われるのが大嫌いだからです(笑)。
基本的には、私の作り方を淡々と見せつつ、「どういう意図で作ったのか」を動画や楽譜と共に解説するだけの内容になります。
音楽家界隈のX(旧Twitter)や各種SNSでは、「音楽理論は必要か否か」といった議論が頻繁に巻き起こります。私個人の意見としては、音楽理論は音楽家にとっての共通言語であり、ただのツールでしかありません。つまり、持っていて当然ですが、それがあるだけで良い曲が作れるほど甘くはない、というスタンスです。
実際、私は音楽理論をはじめ、オーケストレーションやカウンターポイントなど、さまざまな理論や手法を体系的に学んできました。しかし、それらを学んだからといって、すぐに自分の曲のクオリティが上がるわけではありません。それらを基に膨大な数のトライアンドエラーを繰り返すことでしか、曲作りのスキルは向上しないと考えています。
体系的な知識を身につけた後にやるべきことは、それを使ってたくさん曲を作ることです。ただ、どうしてもお手本があったほうが良いですよね。
そんな時にありがたいのが、他のクリエイターが制作手法を公開したり解説してくれるコンテンツの存在です。YouTubeなどにはそういったコンテンツがたくさんアップされており、私もそれらを参考にしながら自分の曲を作り、力をつけました。ただし、こういったコンテンツを探すのはなかなか大変で、ジャンルによっては十分な情報が得られないケースもあります。
私の体感では、ダンスミュージックや流行りの音楽については多くのチュートリアルがありますが、それ以外のジャンルでは十分な情報がないと感じています。
加えて、YouTubeなどにアップされているコンテンツは再生回数を狙ったものが多いため、エントリーレベルの内容は豊富でも、中上級者向けのコアなコンテンツはそれほど多くありません。
現在では、インターネットが発達し、ChatGPTのようなツールも利用できるため、体系的な情報は簡単に手に入ります。そのため、私が作成するオンライン講座では、そうした知識は当然のものとして扱い、その先のケーススタディ部分をできるだけ詳細に解説する内容にしたいと考えています。
何千曲も作ってきた中で蓄えた知識や制作Tipsもありますし、Production Music制作ならではの、尖ったアプローチもシェアする事ができると思います。
完成時期
現在は計画段階のため、具体的な時期をお約束することは難しいですが、目標として9月頃、遅くとも年内中の発表を目指しています。また、より早い段階でデモ版のような小規模なコースを公開する予定もあります。
今後は、このブログやSNSを通じて進捗状況をお知らせしていく予定ですので、ぜひ引き続きチェックしていただけると嬉しいです。