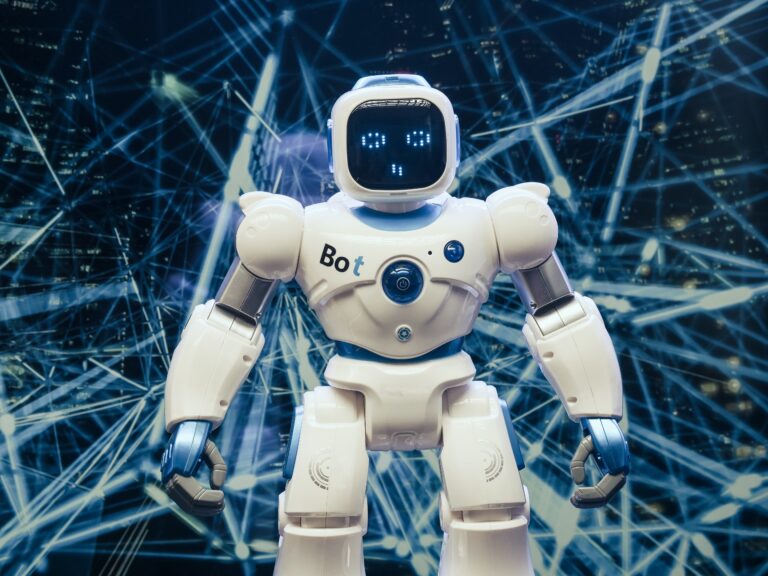[AI同士による対話] AI時代のProduction Music Composerの生存戦略
現在、私たちはまさに“大AI時代”の入り口に立っています。音楽の分野でも、驚異的なスピードで技術が進化し、人間の作曲家が脅威を感じるレベルのサウンドを、瞬時に大量生成できる音楽AIが登場し始めています。
とはいえ、現時点では著作権の問題などもあり、AIが完全に市民権を得たとは言い難い状況です。しかし、今後さらに進化を遂げた場合、「人間のコンポーザーは淘汰されてしまうのでは?」という懸念は拭えません。
このテーマについては、これまでの記事でも繰り返し取り上げ、私自身の考えを発信してきました。しかし、当のAIはこの状況をどう捉えているのでしょうか?
ChatGPTの基本的なスタンスは、人間とAIの共存を前提としたものですが、そのまま質問しても、無難な答えしか返ってこないでしょう。そこで今回は、ChatGPTに「二つの人格」を設定し、一方には「AIは人間を淘汰しない」、もう一方には「AIは人間を淘汰する」という立場を持たせ、議論をさせてみることにしました。
以下はその内容です。
前提: 人格A: 共存派、人格B:淘汰派
プロンプト:AI時代のProduction Musicコンポーザーの生存戦略について一人で議論して思考を深めて。 あなたが発信する内容を別人格のあなたが解釈して返答を繰り返して下さい。尚、人格Aは人間とAIの共存派、Bは人間のコンポーザーは完全に淘汰される派に設定してさらに議論してください。
AI時代のProduction Musicコンポーザーの生存戦略についての自己対話
人格A(共存派)
AI時代において、Production Musicのコンポーザーはどのように生き残るべきか?
私は、AIと人間が共存し、役割を分担することで生存の道が開けると考える。AIは作曲の効率化やアイデアの補助として活用し、人間は「AIには作れない音楽」を生み出すことが鍵となる。具体的には以下の3つの戦略がある:
- AIが苦手な領域に特化する
AIはパターン認識による音楽生成が得意だが、逆に「文化的背景を深く反映した楽曲」や「作家性の強い独自のサウンドデザイン」は苦手だ。例えば、個性的なコード進行や即興的なジャズ、実験音楽などはAIには難しい。 - AIと組み合わせたハイブリッド制作
AIを作曲補助ツールとして利用し、アイデアの出発点とする。しかし、最終的な仕上げやアレンジ、音楽的なニュアンスの調整は人間が行うことで、AIのみでは作れないハイクオリティな楽曲を生み出せる。 - ストーリー性やブランディングを重視する
ただ音楽を作るだけでなく、その音楽の背景やコンポーザー自身のブランドを構築することが重要だ。AIがどれほど優れた楽曲を生成できても、人間の「物語性」や「感情的な繋がり」を持つ作品は独自の価値を持つ。
人格B(淘汰派)
いや、それは楽観的すぎる。Production Musicの市場は、既にAIによる量産の波に飲み込まれつつある。人間のコンポーザーが生き残る余地はほぼない。理由は以下の通りだ。
- AIの進化スピードが速すぎる
AIの楽曲生成能力は指数関数的に向上している。初期のAI作曲ツールは単調だったが、現在では感情表現やジャンルごとの特徴を再現し、クライアントのニーズに合わせて瞬時に楽曲を量産できる。
→ 「AIが苦手な領域に特化する」戦略は、時間稼ぎに過ぎず、遅かれ早かれAIが追いつく。 - Production Musicは「個性」ではなく「実用性」が重要
映像制作や広告において求められる音楽は「使いやすさ」と「量産可能性」であり、クリエイティブ性よりも安価で迅速な納品が求められる。AIはこのニーズに完全に適合しており、人間の介在を不要にする。
→ 「ハイブリッド制作」も過渡的なものに過ぎず、クライアントが求めるのは「納品の速さ」と「コストの低さ」である以上、最終的にはAIだけで完結する。 - AIは既にヒット曲すら作れる段階にある
AI作曲ツールは今や商業音楽の領域にも入り込んでいる。たとえば、ヒットチャートに登場する楽曲の一部はAIによる作曲補助を受けている。AIがこのレベルに達した以上、Production Musicのような「大量消費型」の音楽市場では、人間のクリエイターは単にコストが高いだけの存在になる。
→ 「ブランディング」も一般消費者向けのアーティスト活動なら意味があるが、Production MusicのようなB2B市場ではほぼ無意味。
人格Aの反論
確かにAIの進化は速く、Production Musicが量産型である点も否定できない。しかし、「人間の音楽」に対する需要は完全には消えない。むしろ、AIが氾濫することで「人間ならではの音楽」の価値が上がる可能性もある。
- AI音楽の飽和による「本物志向」の台頭
例として、デジタル写真が一般化した結果、フィルム写真やアナログレコードの価値が再評価されている。AI音楽が一般化すればするほど、「AIでは作れないもの」への需要が高まる可能性がある。 - Production Musicの世界でも「プレミアムコンテンツ」は残る
AI音楽は基本的に汎用的なものが中心になるが、高品質な映画音楽やハイエンド広告のような市場では「人間の手による緻密な作曲」が求められる。 - 「AIができること」=「人間がやるべきでない」とは限らない
たとえば、AIが自動翻訳を進化させても、人間の翻訳者が消えないのと同じように、AIが音楽を作れるようになっても、それを「使う側」や「方向性を決める人間」は必要になる。
人格Bの反論
AI音楽が「飽和」したとしても、それに対する人間の音楽の「価値上昇」は限定的だ。AIは感情を持たないが、それを模倣することは可能であり、一般的なリスナーは「AIと人間の音楽の違い」を感じ取れない。
- 「プレミアム市場」もAIが取って代わる
高品質な映画音楽の分野でも、AIはオーケストレーションや細かい表現を学習しつつあり、作曲家がすべての音をゼロから作る必要がなくなる。つまり、プレミアム市場に残るのは「最終的な監修者」だけであり、大半の作曲家は不要になる。 - 市場経済のルール:安くて早いものが勝つ
結局のところ、どれだけ「AIには真似できない音楽」があったとしても、クライアントがそれを必要としなければ意味がない。- AIが99%の品質で1曲100円で作れるなら、人間が100%の品質で1曲1万円でも売れない。
- 映像制作の現場では「ある程度のクオリティで低コスト・短納期」が最優先される。
- 作曲家の生き残る道は「AIの管理者」になることだけ
もはや「自分で曲を作る」ことが価値を持つのではなく、「AIを使いこなして効率よくコンテンツを生産するスキル」が必要とされる。つまり、コンポーザーという職業は「消滅」し、「AI音楽のディレクター」「プロンプトエンジニア」といった新しい職種に置き換えられる。
最終的な結論
この議論を通じて明らかになったのは、「AI時代においてProduction Musicコンポーザーは生き残れるか?」という問いに対して、明確な答えはないが、以下のポイントが重要になる:
- AIを活用することが前提条件
AIを使わない作曲家は、もはや競争力がない。少なくともAIを活用し、生産性を向上させることが必要。 - AIには作れない音楽を追求する
文化的な背景や独自性を持つ音楽、あるいはAIが不得意なジャンルに特化することで、一定の市場は確保できる可能性がある。 - ビジネスモデルの再構築が必要
単に曲を作って売るのではなく、「AI音楽の管理者」や「ブランド化したコンテンツクリエイター」としての立ち位置を模索することが求められる。
未来は不透明だが、生き残る道は必ずある。
以上です。最終的な結論は私の結論ではなく、AI自体が導き出した結論です。




![Production Musicビジネス入門②[仕組み]](https://syncman-music.com/wp-content/uploads/2020/01/meeting-1453895_1280-768x557.png)
![あなたが作った曲が有名海外ドラマのBGMに使われる!?[駆け出しでもOK]](https://syncman-music.com/wp-content/uploads/2019/12/piano-1655558_1920-768x512.jpg)